ずっとあるかのように思っていたものがなくなる。ずっとあるどころか、有る無しを意識すらしなかったものが消える。
そんな日々に身を置いていた。
街の一角、空き地になってから、ここには前何があったっけ?と考えるような。
記憶はあやふやで、指の隙間から砂が溢れるように、落ちていく。
私が撮るようになったのは、記憶を信じられなくなっていた時だった。
だから、撮ったんだろうな。そして、怖くてずっと撮っていたのかもしれない。
すごく好きだった亡くなった方の書いた物語。女の子の記憶を追って、遠く旅する。
物語の最後、それまで冷静に低い温度で寄り添っていた一緒に旅をした男の子が、「頼みがあるんだ」と言う。
「オレのこと避けないでくれないかな」
「あなたのことを知っているといるからという理由で、オレを悪い記憶の引き金のように扱わないでくれないかな」
物語は最後の1頁までわからない。
あれは女の子だけの物語ではなかった。
きっとそんな風に生きている。自分だけの物語じゃない。絡みあって流れていく。
それをちゃんと忘れないようにしないと、自分のために誰かをぞんざいに扱うことになる。
自分のために誰かを踏むことになる。
そうした生き方は自分に返ってくる。
もし、踏むことがあったら、無意識にではなく、ちゃんと意識して痛みを知りながら踏まなきゃいけない、と思う。
物語は最後の1頁までわからないから。
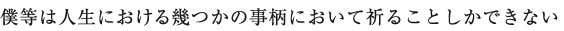

Gosh, I wish I would have had that inromfation earlier!