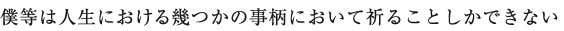中学生の頃ぐらいから、こっそりと家を抜け出して、ふわふわと夜歩くようになった。
繁華街へ遊びに行くようなものではなく、ただ誰もいない道を歩いた。
昼間とは顔の違う、誰もいない学校の校庭に忍びこんだりもした。
そんなに多くはない友達と、時々待ち合わせをした。
何をするわけでもなく、少し話して、書いた手紙を交換して別れる。
次の日、また学校で会うのに。
夜は、昼よりも優しかった。
小さな秘密。スリル。
“特別”が欲しかったのかもしれない。
夜が好きなのは今も変わらない。
しんとして何も聴こえない、もしくは風の音だけ、雨の音だけ聴こえる夜は柔らかく馴染む。
「似てない僕らは細い糸で繋がっている 良くある赤い奴じゃなく」なんてもう信じていないけれど。
遠く滲む朝陽の色を遥かに。