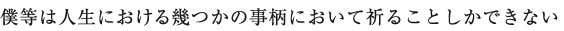どんなに陽の場所でも、窓を開けて空気をかき混ぜなければ澱む。
男木島は陽の島だと思う。昔から住む人は好奇心旺盛で新しいものに対して躊躇よりも、知的欲求の方が勝つ。新しく移り住んだ人は、それはこんな辺鄙な島に住むくらいだから何かどこか芯を持っていて、ここに住むということだけじゃなく前を向いている。
それでも、どうしてもうまく風が通らなくなる場所がある。それも含めてのコミュニティだと思っていたけれど、その空気を風どころか嵐みたいにかき混ぜるまれびとが来た。
まれびとの名前はきゅうかくうしお、という。
嵐と言っても不快ではない。少なくとも私には。
2025年8月8日から10日の3日間のパフォーマンス。3日のための準備は足掛け2年。何度も足を運びコミュニケーションを取って、ここで何を作るか、島という場所と人とを丁寧に調べながら、そして自分たちのインスピレーションに従いながら進めてきた。(ように見える)
「祭り」が気になる、という話が出たのはいつくらいだったろうか?男木島の大祭りは2年に1回。2025年。瀬戸内国際芸術祭の年は祭りは「無い」年だ。2024年、大祭りを見にきたきゅうかくうしおの姿があった。
祭り、ねえ。祭り。お祭りはちょっと難しい。みんなにとって大切なものだから。神事として、歴史として、島の中の合意形成の場として、政り的なものとして、どの角度から手に取っても触っても難しい。
そこが気になると、まれびとは言う。
きゅうかくうしおは、一つではない。でも一つでは無いけど一つでもある。踊り子の2人を中心にしているようで、実は「中心」なんてない集団のように見える。まれびとが外から来たように、私も彼らにしたら外の人なので勝手なことを言う。それぞれがやることのど真ん中を持っているのに、レンジは広くて気がついたら他のことをしてたりする。どれだけ真剣に本気に遊んでいるんだろうかと思う。
そんなまれびとが、祭りに手をつけた。いやあ、ねえ、大変よ、これ。しかも、勝手にやるんじゃなくてできるだけ合意形成を作ろうとする。尊重しようとする。それが既にこれお祭りですね。
男木島の大祭の屋台は2週間みっちり練習するのだけど、きゅうかくうしおのお祭りは東郷清丸さんが島から島へと毎週旅してきてくださって6月から音楽隊は練習開始。
めいめいに弾きたい楽器を持っていく。清丸さんがそれにあわせて(そして多分それぞれの力量にあわせて)楽譜をかきおこしてくれる。なんて贅沢。
そう、いわば最初の関わりからずっと贅沢な時間でしかなかった。どんな風に作品が作られていくのか特等席で見ている、参加させてもらっている。
3日間のパフォーマンスは、インターネットの海にいくつか流れているし、きゅうかくさんでもきっと出すと思うから、言葉は無しで。見て感じるのがきっと一番良い。
とにかく持っていかれる。最後のパフォーマンスは圧巻だったし、それを見た島のおばあちゃんが「良かった。こういうの好きかも」と言っていたと聞いた。伝える機会がなかったのでここに書いておく。
まれびとは來て、素晴らしい偶然を結んで、ひらいて、去っていく。

2013年の瀬戸内国際芸術祭、昭和40年会というアーティストグループがきっかけで、男木島の小中学校が再開した。あれもまれびとだったのだと、今思う。外から来てなにかをもたらして去っていくもの。
今回、きゅうかくうしおが何をもたらしたのか、わかるようでわからない。形としては何も残らないのかもしれない。
それでも、なんだかきっと確かに残っていて、空気が澄んでいる。
ちなみにまれびとは神と同義語らしいけれど、神というよりみんな化けもんみたいだったことも書いておく。肉体のお化け、コミュ力のお化け、なんでもできすぎるお化け、声のお化け、体力のお化け、気遣いのお化け、調整のお化け、明かりも衣装もご飯も、人は何かを真剣に突き詰めて、真剣に遊ぶとお化けになるのかもしれない。
お化けにたちに遊んでもらった夏だった。